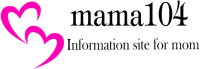11ヶ月でハイハイしないのは?つかまり立ちでいきなり歩く子も

「11ヶ月でハイハイしないと練習させるべき?」周りの子よりハイハイする月齢が遅いと、ママは焦ってしまいますよね。
11ヶ月でハイハイしないのは、うつぶせ寝が嫌いな場合が多いです。ハイハイをすっ飛ばして、いきなりつかまり立ちする子もいるため、心配しなくても大丈夫ですよ。
ハイハイが遅い原因を知って、ママの不安を解消してみませんか?
Contents
ハイハイしない赤ちゃんはシャフリングベビー

シャフリングベビーとは?
ハイハイしないでお尻だけで移動する子のことを「シャフリングベビー」といいます。日本名では別名「いざりっ子」ともいいます。
シャフリングは英語の「shuffle」で、日本語訳にすると「いざり」です。
Shuffleの意味は「足を引きずって歩く」で、直訳すれば順番を入れ替える、混ぜ合わせるという意味があります。シャフリングベビーは通常の子どもと順番が違っていて、なかなかハイハイをしません。
寝がえりやうつぶせの姿勢が極端に嫌いなことが多い
シャフリングベビーは寝返りやうつぶせの姿勢を極端に嫌う場合が多いです。
うつぶせ寝をしないとハイハイの体勢にならないため、ハイハイするための筋力発達が遅れる傾向があります。寝返りもできないのではなく、嫌うため寝がえりの回数が少ないのが特徴です。
赤ちゃんがハイハイする時期

赤ちゃんのハイハイは8ヶ月ごろから
赤ちゃんがハイハイし始める時期は、生後8ヶ月ごろです。首が座って寝返りができるようになると、赤ちゃんは自然とお座りの姿勢になります。
必ずしもすべての赤ちゃんが、生後8ヶ月でハイハイするわけではありません。子どもの成長に個人差があるように、ハイハイに必要な筋肉の発達もそれぞれです。
お座り、ずりばい、ハイハイの順番で進む
多くの赤ちゃんは、ひとつの経過を経てハイハイへと移行していきます。
首が座る→寝返りができる→お座りをする→ずりばい→ハイハイの順番です。その後はつかまり立ちをはじめて、一人で歩けるようになります。
遅くても10ヶ月にはハイハイする子が多い
ハイハイは遅くても生後10ヶ月までにできる子が多いです。そのため、周りの子の様子を見て「うちの子はなんでハイハイできないのだろう?」とママは焦ってしまいます。
検診でも助産師さんや医師に「ママがもう少し促してあげて」と言われてしまうと、自分が悪いのだと勘違いして、自分を責めてしまうママもいます。
1歳でハイハイしない子もいるため心配しなくて大丈夫
ハイハイができる月齢は、その子によって大きく違います。育児書通りに進む子は少なく、それぞれの子によって成長は変わります。
早く成長が進めば「うちの子は優秀」と喜んで、遅ければ「私の育て方が悪い」という考え方はおかしいですよね。同じママが数人の子どもを育てても、その子によって成長は全く変わってくるためです。
11ヶ月の赤ちゃんがハイハイしないのは障害なの?

十分な筋肉が付いていないためハイハイしないだけ
シャフリングベビーは極端に寝返りやうつ伏せを嫌う傾向があるため、ハイハイに必要な筋肉の発達が遅れてしまいます。その子がどうしてもイヤだと感じているため、無理強いはできません。
普通の子の場合は、お座りをして前かがみになることに気が付きはじめます。
前かがみになれば手足を動かせば前に移動することに気が付き、ハイハイができるのです。しかし、シャフリングベビーは前かがみになること自体が嫌いなため、ハイハイの姿勢になるきっかけがつかめないでいます。
ハイハイの魅力に気が付かない赤ちゃんも
シャフリングベビーの場合は、前進にお尻を使っています。移動にはとくに困らないため、ハイハイする魅力に気が付いていないこともあります。
寝返りやうつ伏せを嫌う傾向がないのにハイハイしないなら、ママがハイハイの魅力に気が付かせてあげてみてください。
ハイハイしないだけで発達障害とはいえない
シャフリングベビーは特定の筋肉の発達が遅れているだけで、身体や脳に異常はないです。
心配なのは「言葉が遅い」「首が座らない」「ミルクの飲みが悪い」など総合的なことです。ハイハイしないだけの症状だけなら、その子の成長が遅れているだけなのでしょう。
11ヶ月でハイハイしない赤ちゃんのトレーニング方法

11ヶ月でハイハイしないのが気になるなら、トレーニングすることもできます。
タミーマイムで筋肉を鍛えるトレーニング
タミーマイムとは、赤ちゃんを腹ばいにさせてトレーニングさせる方法です。
生後すぐから開始することができますが、生後1ヶ月ころ首が安定してからがおススメです。赤ちゃんをうつぶせのまま一人にすると窒息の危険性があるため、必ず誰かが赤ちゃんの様子を見ながらやってください。
月齢が低いときにタミーマイムをやらせないと、ハイハイをやる筋肉が育ちません。生後11か月で腹ばいの運動を嫌がるなら、赤ちゃんの気持ちに任せたほうがいいでしょう。
筋肉の成長が多少遅れても、歩けない子はいないからです。ママが焦らず見守りたいなら、無理に腹ばいのトレーニングをさせない方法もあります。
赤ちゃんの周りにおもちゃを置いて行動を促す
うつ伏せを極端に嫌う子の場合は、周りにおもちゃを置く方法もおススメです。
赤ちゃんの手が届きそうで届かない場所におもちゃを置くと、赤ちゃんは取ろうとして体を動かします。腹ばいになることはなくても、体を前後左右に動かす筋肉は鍛えることができます。
同年代の子と遊ばせて刺激してみる
のんびりな性格の子だと、ずっと座ったままでも平気な場合があります。とくに兄弟がいないと刺激が少なく、赤ちゃんのマイペースで通るため、ずっと座り続けてハイハイが促されないことがあるようです。
「泊まりに来た親戚の子と2~3日遊ばせたら、ハイハイするようになった」というケースはよくある話です。
近くに児童館があるなら出かけて、同じ月齢の赤ちゃんの様子を見せてあげましょう。ショッピングモールやデパートでもベビーコーナーがあれば、違う子の刺激を受けることができます。
11ヶ月でハイハイしないでつかまり立ちで歩くことはある?

ハイハイしないでいきなりつかまり立ちする子もいます
必ずしも「ハイハイしないと次のステップに進めない」わけではありません。うつぶせ寝が嫌いな子でも体は少しずつ成長していき、立つための筋肉が付くと、ある日突然つかまり立ちする子も多いです。
シャフリングベビーは密かに立つための筋肉を養っていて、何か赤ちゃんの興味を引くものがあれば、つかまり立ちすることはあります。
ハイハイしない子は歩くのも遅い傾向がある
ハイハイしないとどうしても筋肉の発達が遅れるため、歩くのが遅い傾向があります。
早い子では11ヶ月になればつかまり立ちするのですが、ハイハイしない子は1歳過ぎてもまだお座りを続けるようです。ハイハイが遅い子の場合は、ようやく歩き始めたのが「2歳目の前」ということもあります。
シャフリングベビーの歩き始めが遅いからといって、その後の体の成長に影響するわけではありません。
その子がたまたまハイハイや腹ばいが嫌だっただけです。2歳や3歳になっていくと、周りの子と比べても体の成長に変わりがありません。
ハイハイが遅くても、その子の個性だと割り切って、育児を楽しんでみてください。
まとめ:11ヶ月でハイハイしなくても見守ってあげよう
今は情報があふれているため「8ヶ月になってハイハイしないと異常」「1歳になってもつかまり立ちをしないのはおかしい」と感じてしまうママは少なくありません。本来子どもはその子の魅力があるはずなのに、周りの子と比べてしまうのはおかしいですよね。
私自身赤ちゃんの頃、座ったらずっと座っている子だったそうです。どちらかというとのんびりタイプのため、子どものころから性格が出ていたのかもしれません。
11ヶ月でハイハイしなくてもその子の個性ですから、見守ってあげてくださいね。
他の育児中の悩みの記事も下記に紹介しておきます。合わせて参考にしてみてください。