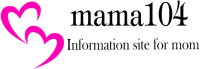イヤイヤ期の夜泣きで暴れる。そんなときの対策方法とは?

「何でもイヤイヤ言うようになり、夜泣きもひどい・・・」「一度夜泣きがはじまったら、手が付けられない」
イヤイヤ期に突入すると日中の対応だけでも大変なのに、夜泣きまではじまるとママはぐったりしてしまいますよね。
0歳児までは夜泣きひとつしなかった子でも、イヤイヤ期になると途端に夜泣きが始まることもあります。
イヤイヤ期の夜泣きはちゃんと理由があるので、なぜ子どもが泣いてしまうのか?イヤイヤ言うようになったのか理解してみてくださいね。
イヤイヤ期の夜泣きが解消されれば
- ママも子どももぐっすり寝られる
- 日中のイヤイヤの対応もわかる
- ママのイライラが減る
イヤイヤ期の夜泣きは子どもにとっても問題を抱えているので、その原因を知って適切な対策をしてみましょう。
Contents
イヤイヤ期で夜泣きする理由とは?

イヤイヤ期の夜泣きで悩んでいるなら、まずはその理由を知るようにしましょう。子どもにとって何か問題があるのに、問題が解消されないため夜泣きをしてしまうのです。
昼間に嫌な体験をしたため夜泣きする
イヤイヤ期に入ると「何でも自分でやりたい」「自分の思い通りにしたい」という気持ちが出てきます。するとママやお友達とのやりとりでも不満が出てくるもので、日中の不満がストレスとなり、夜泣きに繋がることがあります。
だからといって何でも子どもの言いなりになればいいわけではありません。「新しいお菓子が食べたい!」と子どもがイヤイヤ言い出しても、ママは簡単に認めないようにしましょう。
「ママが自分の言いなりになる」と学べば、子どもは毎回そのような行動をおこすようになります。子どもがイヤイヤ言い出してうるさいから、親はお菓子を与えてしまう、ということは避けましょう。
「泣いてもお菓子はもらえない」「イヤイヤ言ってもお菓子は手に入らない」ことを理解すれば、子どもも学習してくるはずです。イヤイヤ期は子どもが社会性を学ぶ時期でもあるため、日中に自分の思い通りにいかず嫌な思いから夜泣きにつながるのは仕方がないことです。
またイヤイヤ言い出す子どもの主張もちゃんと聞いてあげること。家庭のルールがあるならそれを守らせるのは当然ですが、その意味を理解していない子どもは自己主張してきます。
「〇〇ちゃんの気持ちはわかった」「でも〇〇はできないんだよ」と子どもの気持ちに寄り添ってあげると、イヤイヤ期を早く卒業できるようになります。イヤイヤ言うのはただのワガママではなく、ママがちゃんと話を聞いてくれないことに対する怒りの場合もあるからです。
眠りが浅いため夜泣きする
イヤイヤ期になってくると子どもも体力がついてくるので、昼寝をしなかったり日中に遊びすぎたりして生活が不規則になることがあります。
大人も毎日の生活のリズムが狂うと、とたんに夜寝られなくなりますよね。その典型的なのが旅行のときではないでしょうか。せっかくの旅行だからと思って遊びすぎると、普段の生活とリズムが変わってしまい、なかなか寝付けなくなってしまった経験がある方も多いはず。
イヤイヤ期の子どもも生活のリズムが狂い、寝付けなかったり、寝ても眠りが浅かったりして、夜泣きしてしまうことがあります。
小さな子どもがいる家庭では、親の都合で子どもの生活リズムを狂わせないようにしましょう。イベント時でどうしても同じような生活リズムにできない場合は、夜泣きするのをあきらめるしかありません。
保育園に通い出すなど環境が大きく変化した
イヤイヤ期に夜泣きが始まる理由のひとつとして、生活の変化が挙げられます。ママが仕事をはじめて子どもが保育園に通い出せば、子どもにとって毎日刺激がかかりすぎます。
生活が大きく変化したときの夜泣きは簡単に改善できません。とにかく子どもが新しい生活に慣れてくれるまで、夜泣きは続くと考えましょう。
「こんなに大変なら働かなければよかった・・・」とママは思うかもしれません。生活の変化による夜泣きはずっと続くことはないので、もう少しの辛抱です。
イヤイヤ期の夜泣きにおすすめの対策方法とは?

イヤイヤ期に夜泣きがおきた場合、3つの対策方法があります。原因別の対策をすることはもちろんですが、夜泣きの原因がわからない場合は次の対策がおすすめです。
しっかり目が覚めるよう起こす
イヤイヤ期で夜泣きする場合は、一度しっかり子どもを起こしてください。もしかしたら嫌な夢を見ただけかもしれませんし、寝ぼけているだけかもしれません。
現実と夢の区別がつきにくい年齢のため、しっかり目覚めさせるのがポイントです。夜泣きをはじめたら違う部屋に移動して電気をつけます。
目をしっかり覚まさせるために、冷たい飲み物を与えるのもおすすめ。テレビを一緒に見たり、お風呂に入れたり、外を散歩したり。少しママが子どもにお付き合いする覚悟が必要です。
もしかしたら数日間は朝まで起きているかもしれません。それでも日中は普通とおりに子どもを起こして、昼間はよく体を動かすようにし、お昼寝の時間は夜に影響がない時間帯までに留めます。
日中に太陽の光に当てて遊ばせるようにすれば、暗くなると自然と眠くなるようになります。ママが寝かしつけで悩んでいるようなら、下記のネントレの記事も合わせてご覧になってください。
ママがトントンして安心させてあげる
子どもが夜泣きしてしまう場合、子どもも何か不安を感じているはずです。ママがトントンして安心させてあげると、夜泣きがおさまることもあります。
ときには暴れたり、痙攣をおこしたりすることもあるでしょう。痙攣をおこしても危険性がないようなら、ママは慌てず様子を見るようにしてください。
子どもが布団から出て歩き出してしまうようなら、ママは危険がないよう対処しましょう。布団の上で暴れる、痙攣をおこすようなら、周りに物を置かないで様子をみてあげてください。
子どものイヤイヤの理由に向き合ってみる
イヤイヤ期がはじまってくると「思い通りにいかずイヤイヤ」「でも気持ちを上手く伝えることができない」ために日中もイヤイヤ言い出して、夜泣きにまでつながってしまいます。
子どもも何か理由があってイヤイヤ言っているはずなので、子どもの気持ちに寄り添うことが大切です。嫌なことがあってもママがちゃんと自分のほうを見てくれないから、さらにイヤイヤはエスカレートしてしまいます。
子ども自身もやってはダメなことをわかっていても、どうやって解決したらいいのかわかりません。「イヤイヤが激しい」「この子は育てにくい」と感じる子どもの場合は、親がちゃんと子どもの気持ちに寄り添っていないことが多いようです。
私も子どもが大きくなって子ども自身から「どうしてダメなのかがわからなかった」という言葉が出てきたことがあります。そのとき「わからないからイヤイヤしていたんだ」ということが初めてわかりました。親にとって当たり前のことでも、子どもにとってダメな理由がわからないみたいなのです。
親にとって「幼稚園に行くのが当たり前」「片付けるのが当たり前」だと思っていても、子どもにとってはわからない。その説明を省いていないかママはもう一度考えてみてください。そして親の当たり前は本当に常識なのか?やらないとダメなのか?も考えてみましょう。
親がきちんと説明して子どもに納得してもらえば、イヤイヤは自然とおさまってきますよ。
イヤイヤ期の夜泣きは子どもの気持ちを理解しよう

子どものイヤイヤがおきてしまうのは、子どもが「親の言っていることがわからない」「なぜダメなのかわからない」ときも多いようです。そのストレスが溜まっていけば、夜泣きになるのは当然のことでしょう。
イヤイヤ期に入って夜泣きするようになったら、子どもの気持ちに寄り添ってあげてくださいね。すると日中のイヤイヤも少しずつ減っていき、夜泣きも改善する可能性があります。
ママのその家事は子どもの気持ちより重要ですか?少しぐらい食べ物がいいかげんで、部屋が汚くても死にはしませんが、子どもの気持ちを理解してあげないと心の発達に影響がおきて、一生後悔するかもしれませんよ。