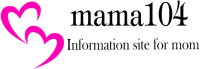寝かしつけを抱っこでするのは間違い?!ママが眠りを邪魔している事実とは?

「ぐずると抱っこしないと寝てくれない」「毎日抱っこの寝かしつけでくたくた」
毎日抱っこでしか赤ちゃんが寝てくれないと、ママも大変ですよね。
実は、ママの抱っこの寝かしつけが、赤ちゃんの眠りを妨げていたのです!
「抱っこでの寝かしつけはよくないの?」と疑問に思いましたよね。そうなんです、抱っこでの寝かしつけ自体が、赤ちゃんの眠りを妨げていたことを知らなければなりません。
抱っこしない寝かしつけ方法がわかると
- 毎日の寝かしつけが楽になる
- 長時間抱っこしなくていい
- ママの時間が確保できる
長時間抱っこして赤ちゃんを寝かしつけする必要がなくなれば、ママの趣味の時間も取れて一石二鳥ですよね。腕も痛くなりませんし、赤ちゃんの睡眠も確保できるようになります。
それでは、抱っこの寝かしつけの何がダメなのか、詳しく見ていきましょう。
寝かしつけで抱っこをするのは実は間違いだったその理由

ママが毎日苦労して抱っこで寝かしつけ、それ自体が間違いだったのです。抱っこで寝かしつけしようとすればするほど、赤ちゃんの眠りを妨げてしまいます。
抱っこをしていると赤ちゃんが暑い
ママが赤ちゃんを抱っこしていると、肌が密着して心地よいのと反面に、暑すぎるデメリットがあります。とくに夏の猛暑に赤ちゃんを抱っこで寝かしつけようとすれば、ママも赤ちゃんも汗でびっしょり!ということも多いですよね。
人が眠たくなるのは、体温が下がったとき。ママが赤ちゃんを抱っこし続けていれば、体温が伝わって赤ちゃんの体温が下がることができません。
抱っこだと赤ちゃんの眠りを妨げてしまう
第二に、抱っこだと赤ちゃんの眠りを妨げるデメリットがあります。
たとえばママも、次のような経験があるはず。長時間の旅行で横になることができず、「結局よく寝られなかった」という経験です。
人は横になればぐっずりと深い眠りにつくことができますが、上半身が起き上がっていると、熟睡できないものなのです。体がおきていると寝られないのは赤ちゃんも一緒で、ママがよかれと思って抱っこしているその姿勢が、赤ちゃんの眠りを妨げます。
抱っこから添い寝の瞬間に目が覚めやすい
さらに抱っこから添い寝に移動しようとしたら、赤ちゃんがおきてしまう可能性があります。長時間苦労して抱っこで寝かしつけたのに、布団に赤ちゃんを置いた瞬間「ギャー」と泣き出してしまうことはよくある話です。
赤ちゃんはまだ上手く自分で眠ることができないので、ちょっとした刺激でも目を覚ましてしまうのです。結局布団に置いても寝付いてくれず、ママが長時間抱っこしてようやく赤ちゃんが寝てくれる、なんてことも多いですよね。
大人だって、ぐっすりと寝ていたのに、体を動かされたら目が覚めてしまいます。そのときの気分は最悪で、大人でも文句を言いたくなるはずです。
抱っこでの寝かしつけが癖になり抱っこしないと寝なくなる
最後に、抱っこでの寝かしつけは癖になるので避けたほうがいいです。赤ちゃんは何度も練習していけば自力で寝付くことができるのですが、抱っこで毎回寝かしつけていると、抱っこが癖になり抱っこしないと寝ない子になるでしょう。
そうやって、抱っこしないと寝ない子ができあがっていきます。まさかママが抱っこして寝かしつけているのが、寝ない子を育てているとは思ってもみませんよね。
抱っこで寝かしつけはいつまで?

抱っこでの寝かしつけは、そもそも新生児のころからやりません。新生児は1日の大半を寝てくれるので、このころから生活のリズムを付けさせて、自分で寝る練習をさせます。
新生児のころから抱っこしないで寝かせる方法は、「ネントレ」ともいいます。0ヶ月の赤ちゃんからネントレをはじめると、生後3ヶ月ごろには睡眠のリズムがつくようになって、自力でも寝る子になっていくでしょう。ネントレをしていれば、遅くても6ヶ月までにリズムが整うことが多いです。
すでに抱っこでの寝かしつけが癖になっている場合でも、今からでもネントレは遅くありません。ママが「抱っこでの寝かしつけを止めたい!」と思ったときが止め時です。
正しい寝かしつけは抱っこではなく添い寝

それでは、生後0ヶ月からできるネントレの方法を紹介します。正しい赤ちゃんの寝かしつけ方法は抱っこではなく、添い寝であることを覚えておきましょう。
新生児の赤ちゃんは2時間ごとに授乳が必要
新生児の赤ちゃんはまだ胃が小さいので、一度に母乳を飲むことができません。そのため2時間おきに授乳が必要で、母乳やミルクを飲んでお腹がいっぱいになったらまた寝るというサイクルを繰り返します。
2時間おきの授乳は、夜中も同様です。そのため夜中に赤ちゃんが泣いたら、授乳を済ませてオムツを交換してやります。
しかしこのとき「夜中の2時間おき」に拘る必要はありません。私の例でいうと、新生児は2時間ごとに授乳が必要なのは知っていましたが、夜中にわざわざ起きて授乳するのは最初の数回のみでした。
夜中にわざわざ起きるのが大変で、赤ちゃんが泣かなかったので朝まで寝てしまったところ、赤ちゃんは朝までぐっすりと寝てくれたのです。「2時間ごとに授乳が必要」だと教科書通りの育児をしようとすると、逆に寝ている赤ちゃんを起こしてしまうので避けたほうがいいわけですね。
私のように、2時間ごとに拘らず、赤ちゃんが泣きだすまで寝かせればいいのです。ママが夜中に「お腹空いていないかな?」「オムツは濡れていないかな?」と気にする行為自体が、赤ちゃんを目覚めさせていることを知りましょう。
生後3ヶ月までに生活のリズムをつける
ママが生後3ヶ月までにやることは、赤ちゃんの生活リズムを整えることです。新生児は昼夜の区別がついておらず、昼でも夜でもかまわず泣き出して起きてきます。
昼夜の区別がついていない赤ちゃんを、たとえば「19時~翌6時まで寝かせる」といった睡眠リズムをつくってやることが大切です。毎日一定の睡眠時間を確保してあげて、「暗くなったら寝る」ことを体に覚えさせましょう。
夜は寝室に赤ちゃんを連れて行くこと
夜19時に赤ちゃんを寝かせることを決めたら、決まった時間になったら赤ちゃんを寝室に連れていきます。寝室は一定の室温を保ち、部屋は暗くしておきましょう。
蛍光灯の灯かりが付いている明るいリビングで寝かしつけはしません。明るい環境では赤ちゃんが眠りにつくことはできないためです。
もちろん、寝室にスマホを持ち込むのもNGです。LEDの強い光は日中の光とよく似ているので、赤ちゃんの目を覚ます原因となります。
徐々に寝る習慣づけをしていく
生後0ヶ月から決まった時間に暗い部屋で寝る習慣がついていくと、子どもも「寝室に移動したら寝る時間」「暗い場所に連れていかれたら寝る時間」だと体で覚えていきます。
さらにおすすめなのが、寝る前に赤ちゃんをお風呂に入れて、一度体温を上げておくこと。入浴後少しして体温が下がってくると、赤ちゃんは自然と眠くなってくるので、この瞬間を利用して寝室に連れていきます。
赤ちゃんを寝室に連れて行ったら、何もしません。ママは添い寝してあげるだけ。すると静かな環境で暗さも手伝って、赤ちゃんは自力で眠りにつくことができるようになるのです。
新生児以降からネントレをさせる方法
誰もが0ヶ月から赤ちゃんを自力で寝かせる習慣をつけさせることはできませんよね。すでに生後半年、1歳になってネントレの存在に気がつくママも多いためです。
赤ちゃんが大きくなってからネントレを始めると、最初は苦労するかもしれません。抱っこしないと寝ない子を寝室に連れて行っても、多くの場合は泣いてしまうでしょう。
それでも赤ちゃんが泣いて寝ないのは、数日間の辛抱です。毎日ルーティンを繰り返して、根気よく寝室で寝かせるようにすると、だんだんと赤ちゃんが泣く時間が少なくなり、自力で寝られるようになりますよ。
夜中に赤ちゃんが起きても放っておく
新生児のころは夜中に寝ぼけて泣くことがあります。授乳やオムツの必要がなければ、放っておくようにしましょう。
赤ちゃんが寝ぼけて泣いているのを、ママがあれやこれやと手を出すと、赤ちゃんは完全に目が覚めてしまいます。夜中に目覚めても自力で寝付く習慣をつけさせないと、「授乳しないと寝ない」「抱っこしないと寝ない」子になってしまうので注意してください。
寝かしつけは抱っこ以外の方法でやろう
赤ちゃんが抱っこでしか寝ないのは、実はママのせいだった?この事実を知って驚いた方も少なくないと思います。
私の場合は、新生児のころから夜中に赤ちゃんが起きることがなかったので、そのまま寝かせるようにしていたら、夜泣きはほとんどしない子になりました。
「自分の眠気を優先したい」という考え方が、結果的に赤ちゃんにとってネントレになっていたようです。夜中は育児書通りに赤ちゃんを起こして授乳やオムツ替えをする必要はありませんよ。
抱っこしないと寝られない場合は、思い切って抱っこを止めてしまいましょう。布団に繰り返し連れて行くようにすると、数日間で赤ちゃんは自力で寝られるようになるはずです。
赤ちゃんを布団に連れて行くだけで寝られるようになると、ママの手間が減り時間もできてきます。ママが添い寝してうっかり寝てしまっても大丈夫なので、赤ちゃんは自力で寝られるように習慣付けていきましょう。
ネントレの方法は、下記の記事でも詳しく解説しているので、合わせてご覧になってみてください。